患者中心の歯科医療は2つの要件を満たしたものでなければなりません。
その要件とは第一に「患者の権利を守る医療」がなされていることであり、第二に「患者の期待に添った医療」が提供されることです。
患者の権利擁護については世界標準の概念であり、地域による違いは受け入れられませんが、第二の要件「患者の期待に添った医療」については、医療が提供される地域の状況や生活・経済レベル、医療受給者の価値観などの要素が考慮されなければなりません。ここでは先ず患者の権利を守る医療について考えてみましょう。
特定非営利活動法人 明日の歯科医療を創る会POS
歯科医療ネットワーク メールマガジン
患者中心の歯科医療Ⅱ |
【患者の権利を守る医療 その1】
〇患者中心の歯科医療
〇患者の権利に関する歴史的背景
![]()
患者中心の歯科医療は2つの要件を満たしたものでなければなりません。
その要件とは第一に「患者の権利を守る医療」がなされていることであり、第二に「患者の期待に添った医療」が提供されることです。
患者の権利擁護については世界標準の概念であり、地域による違いは受け入れられませんが、第二の要件「患者の期待に添った医療」については、医療が提供される地域の状況や生活・経済レベル、医療受給者の価値観などの要素が考慮されなければなりません。ここでは先ず患者の権利を守る医療について考えてみましょう。
| 医療における世界標準(世界医師会総会 1995年9月) 患者の権利 として「患者の権利に関するリスボン宣言」を改訂 |
![]()
患者の権利に関する概念は戦後の国際社会においてコンセンサスを得、国連憲章の中で基本的人権の尊重が謳われたことに端を発しています。特に医療においては、アウシュビッツにおける大量虐殺の最中、医療の発展という美名の基において人体実験が数多く実施されたことへの反省が、現在の医療倫理基盤構築の原点となっています。
第2次世界大戦中のナチスによる非人道的な人体実験は『ニュルンベルク裁判』において裁かれました。人を対象とする実験的医療では、その実験による効果と弊害についての情報開示に基づいた被験者の同意が不可欠な要素であるという『ニュルンベルク綱領』(1947年)となりました。いわゆるインフォームドコンセントの概念の始まりです。
| インフォームド【informed】 | 情報を持った、知識のある⇒情報提供 |
| コンセント 【consent】 | 同意(する)⇒自己決定、選択、拒否 |
その後、1964年の第18回世界医師会総会の『ヘルシンキ宣言』では「被験者となる人は、その研究の目的・方法・予想される利益と研究がもたらすかもしれない危険性、及び不快さについて十分に知らされなければならない・・・研究に参加しない自由を持ち、参加していてもいつでもその同意を撤回する自由があることを知らされなければならない。」「医師は、被験者が研究の内容を知らされた上で、自由意志で行なう同意、すなわちインフォームドコンセントを被験者から、できれば文書によって得ておくべきである。」と明確にされました。
それ以降、世界各地の裁判ではインフォームドコンセント義務違反を主とした判決が採択し、アメリカやヨーロッパでは相次いで「患者の権利章典」「患者憲章」などが制定されています。
1981年第35回世界医師会総会では、患者の権利に関する『リスボン宣言』を採択しています。
この中では「患者が自分の医師を自由に選ぶ権利を有する」「患者は十分な説明を受けた後に治療を受け入れるか、または拒否する権利を有する」と宣言しました。
その後1995年第47回世界医師会総会ではより明確に患者の権利を掲げ、その権利擁護への努力を医療者自身の力で成し遂げるようリスボン宣言を改訂し採択しました。
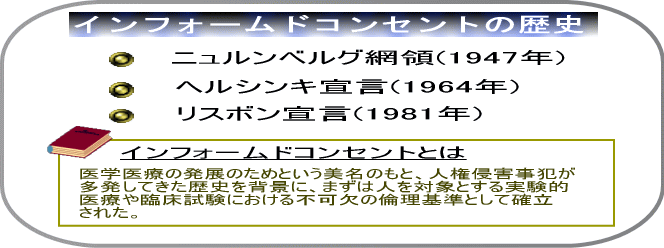
患者中心の歯科医療シリーズ予告
明日の歯科医療を創る会POS
歯科医療ネットワーク メールマガジン 2005.02.07号