患者の権利とは
患者の権利とはどのような内容を含んでいるのでしょうか。
また、その権利の行使にはどのような配慮がなされなければならないのでしょうか。
患者の権利についてはさまざまな権利宣言によって定義されていますが、基本的には表に示すような要件が含まれると考えられます。
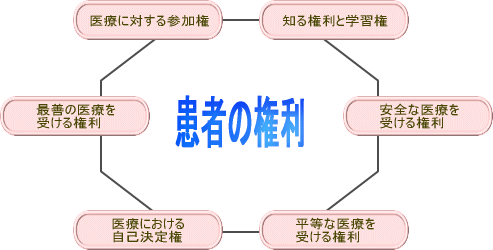
![]()
これは文字通り、患者が主体となって医療に関わらなければならないということです。いわゆる「お任せ医療・お仕着せの医療」ではなく、患者自らが医療政策の立案から医療提供の現場に至るまでのあらゆるレベルに参加する権利を持っているということを意味しています。
![]()
全ての患者は、自分の生命、身体の状況、健康などに関わる状況を正しく理解し、その上で患者自身により最善の選択が出来るように、医療に関わる全ての情報を知り、かつ必要に応じては学習する機会も与えられる権利を持つということを意味しています。近年問題となっているカルテ開示はこの権利を背景としたものです。また学習する権利を行使するに当たっては、素人である患者に対して医療者は専門用語や専門的知識を押し付けるのではなく、正しく理解できるように言葉や方法を考慮し、患者の学習を支援しなければなりません。
![]()
全ての患者は経済的負担能力に関わらず、その必要に応じて、最善の医療を受ける事ができるというものです。昨今の医療経済の環境下では医療の高度化やそれに伴う医療コストの増大などから、全ての人に医療上の最新かつ最善の処置を提供できるとはいえないものの、医療が社会的共通資本としてどのような要件を網羅し、その医療の結果が個々の患者のQ.O.L.を高めるものとなるように配慮される必要があるでしょう。
![]()
全ての患者は安全な医療を受ける事が出来るというものです。医療の対象となる疾患は生命に危険を及ぼすものであることは周知のことですが、医療行為の不確実性、医学に対する習熟度、医療技術の未完成度、使用する薬剤の副作用や合併症、医療施設自体の危険性などさまざまな医療行為自体での問題点により、医療行為を受けることへの危険度が増すと考えられます。医療行為自体が新たな生命への危険要素となってはならないわけであり、常に危険性が適切にコントロールされた状態で医療は提供されなければならないわけです。
![]()
全ての患者は政治的、社会的、経済的地位や人種、国籍、信条、年齢、性別、疾病の種類などにかかわりなく、等しく最善の医療を受けることができるというものです。日本は島国である特徴から人種や国籍に関わる差別的な取り扱いに関しては大きな問題として取り上げられることはありませんでしたが、グローバルな社会となり、多くの外国人が国内での医療サービスを受診する時代を迎えたことを考えたとき、どのような医療体制を確保し、均質な医療を提供できるかは大きな課題となるでしょう。これは医療者のみならず行政を主体とした社会に課せられた責任でもあるわけです。
![]()
全ての患者は十分な情報提供とわかりやすい説明を受け、患者自身が十分に納得した上で患者自身の自由な意志に基づき、患者が受診する医療に対して同意、選択、あるいは拒否する権利を持つというものです。基本的人権を基盤とした患者の人格的自立権に関わる基本原理の一つとされています。患者の生命身体の主体は患者自身であり、このためどのような医療を受けるかについての最終決定権は患者にあるということを謳っています。インフォームドコンセントはまさしくこのことを意味した患者が行なう行為であり、このインフォームドコンセント無しに医療行為が提供されることは患者の特別な状況を除いてはありえません。
患者中心の歯科医療シリーズ予告
- ****患者中心の歯科医療Ⅲ****
- ☆患者の期待に添った医療
- ****患者中心の歯科医療Ⅳ****
- ☆患者中心の歯科医療はなぜ予防歯科医療なのか
明日の歯科医療を創る会POS
歯科医療ネットワーク メールマガジン 2005.03.07号