では、患者は何を望んでいるというのでしょうか?・・・・・・
これを知ることから患者中心の歯科医療は始まるのです。
歯科医院には、受診する患者さんの情報収集のために、問診票・治療申込票などが用意されています。
この中には、治療について下表に挙げるような治療に対する希望を聞く項目と、直接的な身体的情報を聴き取るための項目などが、
整列されています。
|
||
|
|---|
患者の期待を聴き取ったことにはなりません。
これらの項目は医療者が主体となる医療を前提とした、医療者が効率よく治療を進める為に
必要な項目の羅列といえるでしょう。
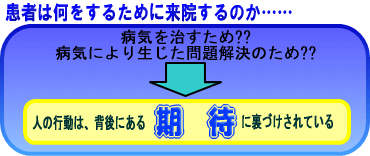
虫歯治療が必要となる患者は、虫歯という病気を治すために来院していますが、虫歯により発生している痛みがあるために快適な日常生活を送れない状況を改善するためだったり、また食事毎に食べ物が虫歯の穴につまり、毎食後虫歯の穴に詰まった食べ物をとらなければならないという生活上の不都合を治すために来院しているということです。
なぜなら・・・
生活上に不都合を感じない場合(時)には、患者行動の優先順位が上がらず来院しないからです。 実際に、“C4”レベルのカリエスになっていても、来院しない患者にその理由を聴くと、その歯が使えなくても、他の歯で食事をする事ができたから問題がなかったのだといいます。
ですから・・・
最初のステップとしては、この患者が改善したい生活上の不都合を、うまく聴き取ることが重要となります。
その期待を明確にして聴き取るということが必要です。
先の来院したケースで評価するならば、毎回の食事の時に詰まった食片を取り除かなければならないことが、日常生活における問題点として
来院した患者に対して、その背景の期待を聴きだしてみると・・・・・・
「おいしい食事を楽しむ事が、私の愉しみであり、今の状態では食事が煩わしくてとても楽しめる状況ではない」
このような理由を訴える患者であれば、この患者には「おいしく食事を愉しみたい」という“真の期待”がある事がわかります。
また、「仕事柄、接待で人と食事をする事が多いが、相手に食事が進まない様子を察知されると人間関係が上手くいかず、結果仕事に影響が出てしまう。仕事に影響を出さないために大きな虫歯の穴を治しておきたい」
このような理由を訴える患者であれば、この患者には「仕事を上手く展開したい」という“真の期待”があることになります。
このように“真の期待”を聴き取る事が、患者の期待を明確化することであり、この手法が一定のスキルに基づいた『コミュニケーションスキル』なのです。
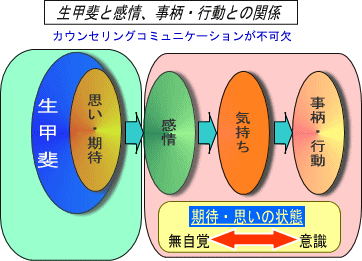
ですから、この期待が大きな・・・そして、いかなる代償を支払ったとしても手に入れたい物であったならば、人はその期待を手に入れるまで行動を持続します。この点を理解した上で、歯科医療に関わる情報を提供していくのです。
患者自身が『予防の定義に基づき、生涯に渡り歯を無くさないように使い続けていく医療者の支援が、結果として患者の“真の期待”の達成に繋がっている事を認知した場合には、患者は予防歯科医療への関わりを、自らの意思で継続する事になり、いわゆる『自発的健康獲得行動』が定着します。
予防歯科医療を目指す歯科医師の方々のよくある質問で「メンテナンスに患者が継続してこない」というものがあります。これは患者の“真の期待”を軸としたアプローチが適切なコミュニケーションによって構築されていないことの典型的なパターンと言えるでしょう。
特定非営利活動法人 明日の歯科医療を創る会POS
歯科医療ネットワーク メールマガジン
2005.08.01