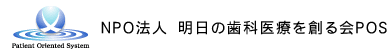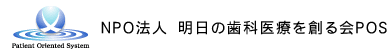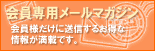|
保険でメンテナンスを、PMTC、エアフロー、ブラッシング、スケーリングをやっています。最初、患者を増やすということではじめましたが、30分以上かかり、人数が増えると大変です。自由診療にしたいのですが、どこで自由診療に変えれば良いのかわかりません。教えてください。 |
 |
先生自身が何を目的にメンテナンスを行ない、どのような効果と結果を求めているかによって変わると思います。メンテナンスが患者確保の手法なのであれば、割り切って安価に提供するべきですし、先生自身がお考えになる良質の歯科医療提供のためのものならば、その主旨をしっかりと患者に伝え、その価値を正当に評価できる価格で提供すべきでしょう。まず保険ありきの発想で出発するのではなく、先生の関わる患者がどのようになることが先生の目的なのかに照らし合わせ、必要な事をするために必要なコストがどの程度なのかを見極めて、そのコストの支払方法として保険と自費の振り分けをされることが良いでしょう。患者が安易にメンテナンスを受診してもその意味を理解できていなければ、先生の望む結果が患者に提供されないのではないかと思いますがいかがでしょうか。 |
 |
最初、保険主体から自費に移行(予防処置)するにはどうしたらよいですか?PMTC的なものを保険でやる方法、最初からやるには値段の設定の問題、人間ドック的なものをやるには金額をどうしたらよいのか? |
 |
ご質問が費用設定の問題であるならば、基本的な自由診療の値段設定はあらかじめ決めておかれることをお勧めします。その費用が決まらない場合は、希望年収から時間コストを計算してみてください。
たとえば、税引き後自由に使える年収が1,000万円必要とします。税引き前所得は約2,000万円、経費率を60%とすると年商5,000万円となります。年間の総診療時間が2,000時間とすれば、1時間あたりの必要売上額は25,000円です。
キャンセルなどを考慮して稼働率を80%と考えると31,250円となります。
この売上をどのように作るかですが、ドクターの診療が1時間あたり20,000円を生産するならば、不足は歯科衛生士に依存するとして、1時間当たり12,500円の売り上げになるように費用設定すると良いでしょう。
ご質問が自費型のシステム導入のことでしたら、現在出上がっているシステムを準用するならば、保険中心の中でまずは週に半日からはじめ、このコンセプトについてくる患者を開拓し、アポイントが埋まればその時間を1日・2日‥と増やしていった場合、5年程度ですべてを現在のシステムに切り替えることができると思います
|
 |
最初、保険主体から自費に移行(予防処置)するにはどうしたらよいですか?PMTC的なものを保険でやる方法、最初からやるには値段の設定の問題、人間ドック的なものをやるには金額をどうしたらよいのか? |
 |
足立 優歯科診療所では、精密検査(デンタルドック) 1時間、検査結果報告 1時間、健康管理計画の相談
1時間で、3万円の費用をいただいています。費用に関しては各先生のお考えと医療機関の事情で考えることが重要でしょう。誰かが作り上げた形があるものを導入するという考えではなく、先生が患者への関与を包括的に行ない、なおかつ患者の健康を守るために先生自身が必要と思う情報を集めればよいわけで、それはたとえ保険であっても構わないと考えます。大切なことは、この精密検査の内容のみで採算を取るか、あくまでも予防の方針への導入として患者が納得するための手順の一つと考えるかだと思います。
|
 |
医療をサービスするということは、たとえばある患者がお金が80%しか支払えない場合、お金はここまでしか払っていないからこれ以上はやりませんという対応をとるのでしょうか?サービス業とはそういうものですが、医療もそんな感じでするのでしょうか?それとも支払えない部分はサービスするのですか?サービスについてお教えください。 |
 |
私が「保険」と「自費」の違いに関して患者に説明する場合、以下のような内容をお伝えします。「保険でも自費でも治療行為を行うことは可能です。しかし長期にわたり壊れない長持ちする治療をするということになると別の話になります。たとえば冠を作る場合、慎重に歯を削り、しっかりと歯ぐきの炎症を抑えた状態で精密な型取りを行ない、さらには冠が仕上がるまで暫間的な冠を作成することも必要です。また実際の冠の作成にあたってはミクロン単位の精度のものを作らなければならず、技工士は顕微鏡をのぞきながらの作業となります。さらにそのような精度が再現できる良質の材料を利用する事も必要です。このような要件を満たしてこそ長持ちする治療が行えるわけですが、そのためには『時間』が必要となります。現実的には保険診療で治療を行おうとするとき、設定された安価なコストから採算性を求めるため、十分な時間を使うことができません。この結果は治療の質が悪くなるという状況を招き、長持ちしにくい治療結果となってしまいます。そして、この状況はあなたご自身に受け入れていただかなくてはならない現実となるわけです。つまり、良好な結果を得るために『時間』がかかるということ、すなわち歯科医師やスタッフを十分な時間拘束し、手間をかけるということが自由診療ではできるのですが、これにはコストがかかり、それが治療費に反映しているという実態なのです。このような事情を踏まえてあなたがあなた自身の取り替えのない歯に対してどの様に対処されるかを決めていただくことが重要です。コストをかけて長持ちする最善の処置をしていくか、あるいはコストを抑えリスクも引き受けるか、ご自身でご判断いただかなくてはならないと思います。
|
 |
保険治療でできる事が自費治療とどのように違いがあるのか、医師側は良く理解できるが、その説明が困難。 |
 |
サービスとは、「人の手を介してその人が必要とするものや役務を提供すること」です。ご質問には「サービス業の意味するサービス」と「おまけをする意味でのサービス」とが含まれており、その点を整理されることがまず必要です。さらに、費用を支払えない患者に対するサービスの手法としてこの質問にお答えするならば、まずは「仕事」と「ボランティア」を識別しておくことと、医療の公共性という視点を明確にしておきたいと思います。・仕事とは:社会的分業制の中で社会が必要とする必要性産物(物・サービス)を一定の時間内で生産し提供すること・ボランティアとは:一定の時間内やコストの制限の中では提供できないが、社会が必要とする生産物を提供すること医療はその公共性の高さから「医は仁術」の言葉に代表されるような奉仕のイメージが強いものですが、すべての仕事は種類に関わらず社会的分業性の中に成り立っているものであり、医療だけが特別の扱いになるものではないと考えます。理由として、医療機関はその活動により収益を生み出し、それをスタッフ、家族、業者に対して報酬として分配していることからも明確です。私財を投げ出し、より良い医療提供のために食えない医療機関を経営される医療者はいないのではないでしょうか。さて、「医療は患者のものである」という観点に立ったなら、患者は自分の価値観と環境の制限の中で許せる最善の判断を患者自身の自由意志ですることが重要で、そのことによって患者責任が明確に生じます。「患者のことを思いやって」というパターナリズムの倫理基盤をベースにすると、患者が患者としての責任を考える機会を奪うことになってしまいます。さらに歯科的疾患の慢性疾患、生活習慣病という側面を考慮したときそれはより大きな問題を投げかけます。患者は健康獲得を医療者に委ねるのでは無理があることを直視し、自らが主体となって健康獲得に取りくまなければなりません。そのような理由から、おまけをするような中途半端な思いやりはすべきではないでしょう。価格にはそれなりの理由があるのです。実際にこのようなケースであれば、私はその方の状況で問題解決ができる方法を共にしっかりと考えます。患者の予算内で取り組む代案を提示したり、支払方法で配慮をしたりしています。過去に大学1回生の患者が、貯金とアルバイトの収入での支払いを希望したので、約100万円の治療費を金利なしで4年間毎月2〜3万円の分割で受け付けたこともあります。あるいはその予算内での問題解決に対し、質の高いレベルでの対応が可能な医療機関(たとえば大学病院)などを患者の意向が反映されるような紹介状を添えて紹介することもあります。金額をおまけすることで喜ぶ方は私も含め世の中には多いものですが、逆にそのようにされることを嫌がる方も実在します。善意の押し売りはせず、同じ立場で問題解決の方法をしっかりと考えるようにしています。 |